財政用語の説明サ行
- 災害復旧事業費
災害によって受けた被害の復旧に要する経費です。 - 財産収入
市が所有する財産から生じる収入で、土地や建物の貸付収入や基金の運用利息等の財産運用収入、市が所有する土地や物品の売払いに伴う財産売払収入があります。 - 財政力指数
当該団体の財政力(体力)を示す指数であり、指数が高いほど財源に余裕があるとされています。基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年の平均値で示します。
財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額 - 債務負担行為
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなど、将来の財政支出を約束する行為です。 - 資金収支計算書
行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動(業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支)に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。 - 資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する割合です。
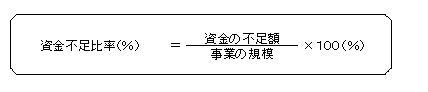
- 自主財源
地方公共団体が自主的に収入できる財源のことで、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入などをいいます。 - 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、赤字の程度を指標化したものです。早期健全化基準は11.25%以上、財政再生基準は20%以上となっています。
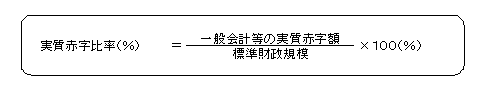
一般会計等とは、財政健全化法の定める会計区分のひとつで、松江市の場合、一般会計、公園墓地事業特別会計、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の3会計です。
- 実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す指標です。実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、起債に当たり許可が必要となります。
18%以上の団体:地方債の発行に国の許可が必要
25%以上の団体:一般単独事業債等の起債が制限
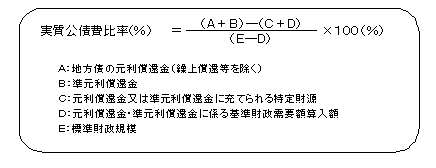
- 実質収支
形式収支から、翌年度の支出がすでに予定されている額を除いたもので、黒字、赤字を判断する指標です。
実質収支=形式収支−翌年度へ繰り越すべき財源 - 実質収支比率
実質収支の額の適否を判断する指標であり、標準財政規模に対する実質収支額の割合で示されます。3%から5%程度が望ましいといわれています。
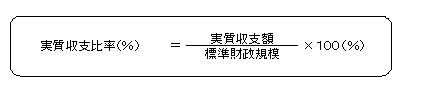
- 実質単年度収支
単年度収支に黒字要素(財政調整基金積立額・地方債繰上償還額)を足し、赤字要素(財政調整基金取崩額)を除外したもので、実質的な黒字、赤字を示す指標です。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立金+地方債繰上償還額−財政調整基金取崩額 - 自動車取得税交付金
自動車取得税の一部を、県が市町村道の延長や面積で按分し、市町村に対して交付するものです。 - 準公営企業
地方公共団体が経営する企業のことで、地方公営企業法の財務規定等一部が適用される企業となります。 - 純資産変動計算書
純資産の増減の状況や、行政コストを経常的な収入で賄うことができているかを把握するための表です。資産の取得のために負担した額が1年間でどのように増減したかを示します。 - 商工費
商工業や観光の振興などの経費です。 - 消防費
消火事務、災害時の被害軽減のための活動や予防など、消防業務に要する経費です。 - 将来負担比率
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化したものです。
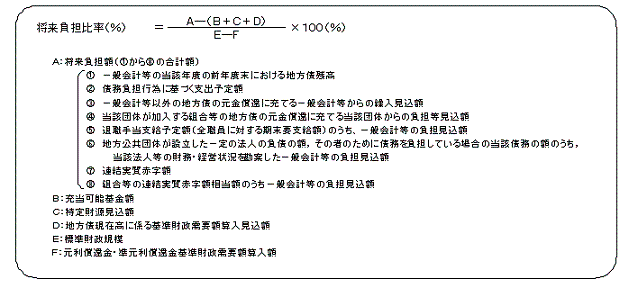
- 使用料及び手数料
使用料は公共施設などの利用の対価として支払っていただく料金で、児童クラブや市営住宅使用料などがあります。
手数料は市が特定のかたに提供するサービスの対価として徴収するもので、住民票や印鑑証明、廃棄物処理手数料などがあります。 - 諸支出金
他の支出科目に分類されない経費をまとめた科目です。 - 諸収入
他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。 - 人件費
職員の給与や議員への報酬などの経費です。 - 総務費
庁舎や財産の維持管理、税金の徴収などの経費です。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 財政課
電話:0852-55-5182
ファックス:0852-55-5070
お問い合わせフォーム









更新日:2025年11月05日