市史講座
松江市史Web講座
「松江市史Web講座」は、『松江市史』や『松江市ふるさと文庫』の内容をもとに、松江の歴史について、Webを通じて気軽に学ぶことのできる講座です。Youtube「松江市公式チャンネル」(外部サイト)で順次公開していきます。
第16回 「戦後80年 松江市の戦争遺跡をあるく―松江連隊遺跡群―」
(2025年8月8日更新)
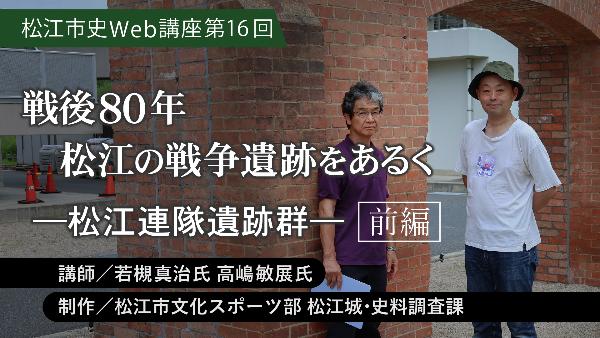
松江市史Web講座第16回「戦後80年 松江市の戦争遺跡をあるく―松江連隊遺跡群―」前編/YouTube動画/39分36秒
(2025年8月22日公開)![]()
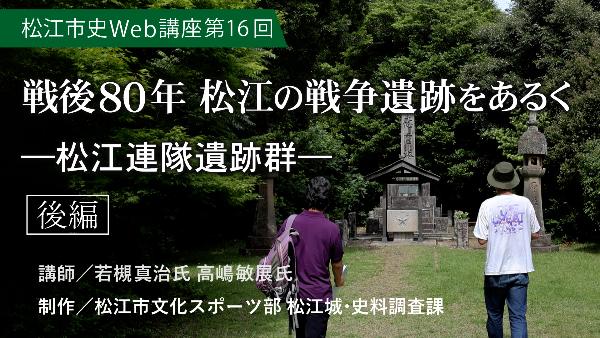
松江市史Web講座第16回「戦後80年 松江市の戦争遺跡をあるく―松江連隊遺跡群―」後編/YouTube動画/28分58秒
【内容】2025年はアジア・太平洋戦争の終戦から80年となる節目の年にあたります。本講座では、島根県で戦争遺跡研究を行っている若槻真治氏と写真家の高嶋敏展氏を講師に迎え、今も残る戦争遺跡を歩きながら、軍都としての松江の歴史をご紹介いただきます。今回は「松江連隊遺跡群」をとりあげます。
【講師】若槻真治氏(「戦後史会議・松江」世話人代表)、高嶋敏展氏(写真家)
【関連書籍】
- 「戦後史会議・松江」企画・制作『島根の戦争遺跡』2021年
- 若槻真治「松江市の戦争遺跡」『松江市歴史叢書』15号、松江市、2022年3月
【関連講座】松江市史Web講座第6回「松江市の戦争遺跡」2022年2月(このページの下をご確認下さい)
第15回「正保城絵図と松江城―絵図に描かれた初期松江城天守の姿―」
(2025年7月4日更新)
【内容】2015年7月8日、松江城天守は国宝に指定されました。今回は国宝指定から10周年となるのを記念し、松江城ブックレット8『正保城絵図と松江城』の著者で、国宝化のための調査に深く関わってきた稲田信先生に、絵図に描かれた初期松江城天守の姿についてお話しいただきます。
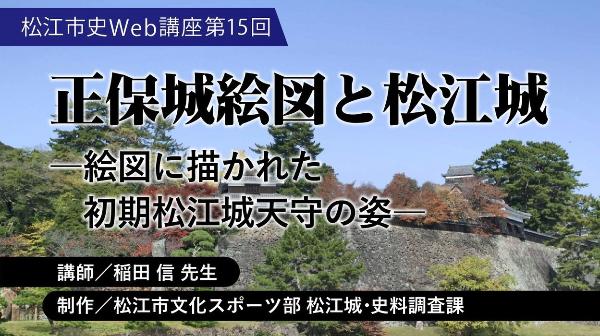
【講師】稲田信先生(松江市客員研究員、松江城調査研究委員会専門調査員)
【関連書籍】
松江市史Web講座第15回「正保城絵図と松江城―絵図に描かれた初期松江城天守の姿―」/YouTube動画/45分19秒
第14回「出雲国成立と山代・大庭古墳群~山代二子塚古墳のナゾにせまる~」
(2024年11月14日更新)
【内容】松江市の茶臼山西麓に位置する大庭鶏塚古墳・山代二子塚古墳は、出雲地方を代表する大型古墳群です。特に山代二子塚古墳は、全国で初めて「前方後方墳」という名称が使われたことで有名です。1924年12月9日に国の史跡に指定されてから今年で100周年。これを記念して開催した講演会の様子を3部に分けてご紹介します。(2024年8月31日、松江市市民活動センター交流ホール)
【第1部】講演1「山代二子塚古墳に眠るのは誰だ!?」

【講師】丹羽野裕(松江市文化財総合コーディネーター)
松江市史Web講座第14回第1部:講演1「山代二子塚古墳に眠るのは誰だ!?」/YouTube動画/44分25秒
【第2部】講演2「日本古代史上における6世紀の出雲」

【講師】佐藤信先生(東京大学名誉教授)
当日配布資料(講演2) (PDFファイル: 322.5KB)
松江市史Web講座第14回第2部:講演2「日本古代史上における6世紀の出雲」/YouTube動画/64分19秒
【第3部】質疑・対談

【講師】佐藤信先生、丹羽野裕
以下の資料で、講演会当日、時間の都合により回答しきれなかった会場からのご質問にお答えしています!(回答者:丹羽野裕)
松江市史Web講座第14回第3部:質疑・対談/YouTube動画/29分04秒
【Web講座特典資料】質疑応答コーナー (PDFファイル: 385.4KB)
第13回「荘園のしくみと暮らし―松江の中世を探る―」
(2024年9月30日更新)
【内容】今回は、日本史の教科書に必ず登場する〈荘園〉について、松江市ふるさと文庫26『荘園のしくみと暮らし―松江の中世を探る―』の著者・西田友広先生がお話します。現在の私たちにとっては複雑な荘園のしくみを、松江市域の事例に基づきながら、具体的に、分かりやすく説明します。

【講師】西田友広先生(東京大学史料編纂所准教授)
【関連書籍】
松江市史Web講座第13回「荘園のしくみと暮らし―松江の中世を探る―」/YouTube動画/49分23秒
第12回「松江藩主の山荘・楽山御立山を歩く」
(2024年8月29日更新)
【内容】今回は、松江藩主の山荘が置かれていた楽山御立山を紹介します。楽山の歴史や役割を学びながら、案内役の西尾克己先生とともに現地を実際に歩いてみましょう。

【講師】西尾克己先生(松江市客員研究員)
【関連書籍】
松江市史Web講座第12回「松江藩主の山荘・楽山御立山を歩く」/YouTube動画/12分05秒
第11回「松江の仏像―山陰最古の木造仏、佛谷寺・木造薬師如来坐像―」
(2024年2月6日更新)
【内容】松江市ふるさと文庫32『松江の仏像―その時代とかたち―』で紹介された仏像から、美保関町の佛谷寺所蔵「木造薬師如来坐像」とその脇侍をとりあげます。著者の的野克之先生とともに現地を訪れ、実際に拝見してみましょう。

【講師】的野克之先生
(島根県芸術文化センター長、島根県立石見美術館長、松江歴史館学芸専門監)
【関連書籍】
松江市史Web講座第11回「松江の仏像―山陰最古の木造仏、佛谷寺・木造薬師如来坐像―」/YouTube動画/11分45秒
第10回「史料でたどる松平治郷(不昧)とその治世」
(2023年9月27日更新)
【内容】「松平治郷(不昧公)研究会」が2020年から2023年にかけて刊行した研究成果を元に、松江市内に伝わる不昧関連史料を、各所蔵機関やゆかりの地をめぐってご紹介します。案内役は研究会副委員長の小林准士先生です。

【講師】小林准士先生(島根大学法文学部教授)
【関連書籍】
- 『不昧の手紙―大圓公手翰を読む―』2020年刊
- 小林准士著、松江市ふるさと文庫31『松平治郷(不昧)の治世―御立派改革後の松江藩政と藩領社会―』2022年刊
- 『松平治郷(不昧公)関係史料集』1、2022年刊
- 『松平治郷(不昧公)関係史料集』2、2023年刊
松江市史Web講座第10回「史料でたどる松平治郷(不昧)とその治世」/ YouTube動画/31分18秒
第9回「七十五膳神事と慶長13年の木椀―松江市野原町―」
(2023年2月27日更新)
【内容】2023年2月20日付で新たに松江市指定文化財となった「野原町八幡宮の七十五膳神事用木椀」を紹介します。八幡宮には古いもので400年以上前の木地椀が数多く伝わっており、現在でもこの椀を使って神事が行われています。この神事の様子と、慶長13年(1608)の椀について分かりやすく解説します。

松江市指定文化財となった野原町八幡宮の慶長13年の木椀
第9回「七十五膳神事と慶長13年の木椀―松江市野原町―」YouTube動画/4分58秒
第8回「史跡出雲玉作跡指定100周年記念シンポジウム」
(2022年11月30日更新)
【内容】松江市玉湯町は著名な玉生産地です。花仙山から採れるメノウや碧玉の原石から作られた玉製品は、その質の高さから古墳時代から古代にかけて各地へ供給されました。花仙山周辺には多数の玉作遺跡が存在し、その代表的な遺跡が史跡出雲玉作跡です。発掘調査により古墳時代から平安時代にかけての工房跡が見つかっており、現在でも花仙山産の原石で作られた玉は「出雲ブランド」と称されています。史跡出雲玉作跡は1922年10月12日に指定を受け、今年100周年を迎えました。これを記念し開催したシンポジウムの様子をご紹介します(2022年10月22日、松江テルサ1階ホール)。
【前編】基調講演「日本列島の国際化に寄与した玉作」

【講師】北條芳隆先生 (東海大学文学部教授)
第8回「史跡出雲玉作跡指定100周年記念シンポジウム」前編/YouTube動画/1時間14分
【後編】鼎談「古代国家の形成と出雲の玉作り」

【パネリスト】北條先生、米田克彦氏 (岡山県古代吉備文化財センター総括副参事) 、永野智朗 (松江市埋蔵文化財調査課学芸員)
第8回「史跡出雲玉作跡指定100周年記念シンポジウム」後編/YouTube動画/59分39秒
第7回「堀尾期城下町絵図の科学的調査in島根大学附属図書館」
(2022年11月1日更新)
【内容】現存する松江城下図の中で最も古い、「堀尾期城下町絵図」(島根大学附属図書館蔵)をご紹介します。今回は絵図に使われている顔料について、東京文化財研究所の早川泰弘先生をお招きして科学的調査を行いました。蛍光X線分析から見えた、思いがけない元素とは?

松江市史Web講座第7回「堀尾期城下町絵図の科学的調査 in 島根大学附属図書館」前編/5分10秒/YouTube動画

松江市史Web講座第7回「堀尾期城下町絵図の科学的調査 in 島根大学附属図書館」後編/12分0秒/YouTube動画
第6回「松江市の戦争遺跡」
(2022年2月18日更新)

- 【講師】若槻真治氏(「戦後史会議・松江」世話人代表)
- 【関連書籍】
- 若槻真治「松江市の戦争遺跡」『松江市歴史叢書』15号、2022年3月発行
- 【内容】松江市内に存在する戦争遺跡についてご紹介します。そもそも、戦争遺跡とはどんなものなのでしょうか。前編では、西南戦争から日清戦争、日露戦争を経て満州事変までの戦争遺跡について。後編では、満州事変以後、日中戦争、アジア・太平洋戦争期の戦争遺跡について、現地の写真や資料とともに解説します。
松江市史Web講座第6回「松江市の戦争遺跡」前編/33分50秒/YouTube動画
松江市史Web講座第6回「松江市の戦争遺跡」後編/44分26秒/YouTube動画
第5回「松江城下の食と人」

- 【講師】小山(松原)祥子(松江市史料調査課主任)
- 【関連書籍】
- 松原祥子著、松江市ふるさと文庫9『松江城下に生きる-新屋太助の日記を読み解く-』2010年3月発行
- 松江市歴史史料集4『御産献立控帳ー松江藩主松平家の料理方小田九蔵の御祝レシピー』2019年6月発行
- 松江市歴史史料集2『大保恵日記1〜5』平成28年4月〜令和2年5月発行
- 【内容】江戸時代の松江城下の人々は何をどんな風に食べていたのでしょうか。城下町遺跡出土の食材や食器、藩主家の献立帳「御産献立控帳」、町人の日記「大保恵日記」などから読み解きます。
松江市史Web講座第5回「松江城下の食と人」23分11秒/YouTube動画
第4回「出雲国分寺の実像に迫る」
大正10年(1921)に出雲国分寺跡が全国初の史跡として指定され、今年で100年を迎えました。これを記念して開催された「史跡出雲国分寺跡指定100周年記念シンポジウム」(主催:松江市、島根県立八雲立つ風土記の丘、令和3年9月19日収録)の内容をご紹介します。
第1部:基調講演、事例報告

基調講演:大橋泰夫先生(島根大学法文学部教授)「古代寺院と出雲国分寺」
国分寺とはどんな寺院かを紹介し、出雲国分寺がどのような姿であったかを、考古学の調査成果をもとにお話しします。
松江市史Web講座第4回「出雲国分寺の実像に迫る」基調講演/58分45秒/YouTube動画
事例報告1:渡邊誠氏(香川県教育委員会)「讃岐国分二寺の調査成果と活用」
四国で唯一の特別史跡讃岐国分寺跡、史跡讃岐国分尼寺跡の調査成果を紹介し、現代における史跡の活用や課題についてお話します。
松江市史Web講座第4回「出雲国分寺の実像に迫る」事例報告1/58分45秒/YouTube動画
事例報告2:飯塚康行氏(松江市史料調査課)「出雲国分寺の調査成果」
出雲国分寺・尼寺成立の背景、発掘調査の経過、今後の整備構想についてお話します。
松江市史Web講座第4回「出雲国分寺の実像に迫る」事例報告2/32分27秒/YouTube動画
第2部:ディスカッション

ディスカッション:「出雲国分寺の実像に迫る」
コーディネーター:川上昭一氏(松江市埋蔵文化財調査室)
国分寺の立地と景観、伽藍配置、出土の瓦文様、史跡の活用という4つのテーマで、講師・報告者がお話しします。
松江市史Web講座第4回「出雲国分寺の実像に迫る」ディスカッション/46分47秒/YouTube動画
第3回「田和山遺跡からみた出雲の弥生社会」

- 【講師】松本岩雄先生(『松江市史』原始古代史部会専門委員、島根県考古学会長)
- 【書籍】松江市ふるさと文庫27『田和山遺跡が語る出雲の弥生社会』2021年2月発行
- 【内容】今回は、松江市ふるさと文庫27『田和山遺跡が語る出雲の弥生社会』の内容を、執筆者の松本岩雄先生が解説します。田和山遺跡(松江市乃白町)の何が特異なのか、出雲の弥生社会でどのような意味を持ち、東アジア世界の中でどのように位置づけられるのか?最新の考古資料を基に、分かりやすくお話しします。
松江市史Web講座第3回「田和山遺跡からみた出雲の弥生社会」前編/22分32秒/YouTube動画
松江市史Web講座第3回「田和山遺跡からみた出雲の弥生社会」後編/30分45秒/YouTube動画
第2回「朝酌・大井の須恵器窯跡群について」

- 【講師】丹羽野裕氏(『松江市史』通史編「原始古代」担当、松江市史料調査課文化財総合コーディネーター)
- 【講演】「朝酌歴史講座」2021年1月20日、朝酌公民館開催
- 【内容】『出雲国風土記』にも記された島根県最大の須恵器窯跡群・大井窯をとりあげます。大井窯の「特別な事情」を考古資料から探り、出雲の須恵器生産の特質を明らかにします。
松江市史Web講座第2回「朝酌・大井の須恵器窯跡群について」前編/37分00秒/YouTube動画
松江市史Web講座第2回「朝酌・大井の須恵器窯跡群について」後編/41分20秒/YouTube動画
第1回「西洋医学受容と衛生思想普及への道のり」

- 【講師】梶谷光弘先生(公益財団法人いづも財団)
- 【書籍】松江市ふるさと文庫24『西洋医学受容から衛生思想普及までの道のり』2020年3月発行
- 【内容】江戸〜明治期の松江の人々が、天然痘やコレラといった感染症、伝染病といかに向き合い、乗り越えていったのかをお話しします。新型コロナウィルスと戦う今の私達にとって、ぜひ知っておきたい郷土の歴史です。
松江市ふるさと文庫Web講座第1回「西洋医学受容から衛生思想普及への道のり」前編/32分12秒/YouTube動画
松江市ふるさと文庫Web講座第1回「西洋医学受容と衛生思想普及への道のり」後編/33分58秒/YouTube動画
松江城web講座
松江城調査研究室「松江城Web講座」が開設されました(詳細は以下のリンク参照)
これまでの取り組み
松江市史講座一覧
これまでに行った松江市史講座の映像(山陰ケーブルビジョン「マーブル」放映済分)は、松江市立中央図書館内でDVDを視聴することができます。視聴をご希望の方は、図書館カウンターへお申し込みください。
松江市史講座一覧表(第1〜142講、平成23年7月〜令和2年3月) (PDFファイル: 194.5KB)
松江市史講座ミニレポート:バックナンバー
これまでに行った松江市史講座(全142講)のミニレポート、および講座資料PDFを、開催年度別に掲載しています。資料PDFのない講座については、史料調査課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 松江城・史料調査課
電話:0852-55-5959(松江城係)、0852-55-5388(史料調査係)
ファックス:0852-55-5495
お問い合わせフォーム









更新日:2025年08月22日